スタッフブログ
薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の薬剤師求人、派遣や単発派遣に関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。
薬剤師の仕事・キャリア
2025.10.01
2025年薬機法改正の全体像とポイント 薬剤師の仕事はどう変わる?

- 薬剤師
- 働き方
- 求人
- 仕事
- アプロ・ドットコム
- オンライン服薬指導
- 薬機法
- 調剤
2025年5月、改正薬機法が公布されました。11月20日以降、2年がかりで段階的に施行されます。薬機法とは医薬品などの製造・販売に関するルールを定めた法律で、製薬企業や薬局・調剤業界のほか、ドラッグストアをはじめとする小売業やスタートアップ企業まで幅広く影響を及ぼします。
特に今回の改正は、薬剤師の仕事内容や働き方に大きな影響を与えます。経営者や薬局の店長、管理薬剤師が把握しておけばよいという内容ではないと考えたほうがいいでしょう。この記事では、薬機法の改正により薬局やドラッグストアで働く薬剤師にどのような変化があるのかを詳しく解説します。
目次
2025年薬機法改正のポイント
2020年以降、製造販売承認書と異なる方法で医薬品を製造するなど、医薬品メーカーの不正が相次ぎました。不正事案に伴ってジェネリック医薬品を中心に医薬品の供給体制が混乱し、対応に苦労した薬剤師も多いでしょう。
また、ネットやIT技術の進化、医療費の抑制、セルフメディケーションの推進など社会全体の変化により、従来の法律では対応できない課題も増えてきました。そこで、国民に高品質かつ安全な医薬品を安定的に届ける体制の作成、薬局機能の見直しなど、多角的な観点から改正が行われました。
海外で承認されている医薬品にもかかわらず、日本での承認が遅れる「ドラッグ・ラグ」、希少疾病用医薬品・小児用医薬品が国内で開発されない「ドラッグ・ロス」も問題視されています。今回の改正では、日本の創薬力強化の対策も行われています。
改正により起こる9つの変化
今回の法改正は、調剤薬局やドラッグストアで働く薬剤師の働き方に大きな影響を与えます。改正された内容の中でも、調剤薬局やドラッグストアで働く薬剤師に関わる部分を中心に紹介します。
1.調剤業務の一部外部委託が解禁
高齢化が進み医療需要が増大していることに加え、薬局やドラッグストアの増加により薬剤師業界は慢性的な人手不足です。薬学部の増加で薬剤師が増えているとはいえ、充足しているとはいえません。
薬剤師不足を補うため、今回の法改正では、医薬品のピッキング、包装、事務作業といった対物業務を外部に委託できるようになります。委託できるのは、同一都道府県内にある別の薬局です。これまで処方箋を受け付けた薬局は、薬局内で調剤を完結させることが原則でした。
時間のかかる定型業務を外部委託できるようになることで、患者様の待ち時間短縮、業務の効率化が期待できます。対物業務を外部委託した分、薬剤師は投薬、服薬指導、健康相談など対人業務により注力することが求められます。地域医療に携わる薬局としての機能強化も目的のひとつです。
外部委託をすると、委託先の体制の確認、薬歴や在庫情報などの共有といった委託先の管理という業務が加わります。また、委託する分、調剤に時間がかかることも懸念点として挙げられています。2年以内の対応が求められているため、2027年5月までに体制を整える必要があります。
外部に委託する薬局で働いている場合、投薬、服薬指導の業務が大幅に増加するでしょう。今まで以上に患者様とのコミュニケーションが重視されます。また、委託先の管理が加わるため、他薬局の薬剤師とのコミュニケーションも発生します。
一方、外部委託を受ける薬局に勤めている場合は、患者様対応よりもピッキングや一包化などの定型業務が増えるでしょう。ただ、技術の進化により、これらの業務はロボットでも対応可能になりつつあります。薬剤師として長く活躍していきたいなら、対人業務を強みとするほうが得策です。
2.薬剤師等が常駐しない店舗での一般用医薬品の販売がスタート
これまで薬剤師や登録販売者がいない店舗や時間帯は、OTC医薬品の販売ができませんでした。要指導医薬品を購入する際は、原則として薬剤師が書面による説明を対面でできる環境が必要でした。しかし、ライフスタイルの多様化により「薬剤師や登録販売者が店舗にいる時間帯に買いに行けない」「薬局が遠いので、近くのコンビニで市販薬を購入できるようにしてほしい」という要望が増えています。
今回の法改正では、一般用医薬品のオンライン服薬指導が可能になりました。2022年の薬機法改正により、処方箋がある場合のオンライン服薬指導は解禁されていましたが、これが一般用医薬品にまで拡大されます。
薬剤師からスマホやタブレット、受取店舗の販売機や店頭端末にて対面のオンライン服薬指導を受けた後なら、薬剤師や登録販売者がいない店舗でも市販薬の購入ができるようになります。
たとえば、夜間に発熱した場合、オンライン服薬指導を受けた後にコンビニで薬が購入できるのです。薬局が少ない地域でも手軽に医薬品を購入できるため、患者様の利便性向上が期待できます。当面は、有資格者が所属する店舗と販売店舗は同一都道府県内にあることが条件となります。
処方箋がある医薬品のオンライン服薬指導は解禁されているとはいえ、経験がある薬剤師は少ないでしょう。オンラインは対面とは異なり、表情や顔色など言葉以外から読み取れる情報が少なくなります。
このような環境の中で、十分に情報の聞き取りができるのか、誤解やミスなく説明ができるのか、不安の声が挙がっています。また、オンライン指導の記録方法、受け渡し店舗の保管・陳列ルールの指導などもこれから定まっていく見通しです。施行から2年以内の2027年5月までの対応が求められます。
オンライン服薬指導が実現すると、働く時間が変化します。特に、24時間営業のコンビニで薬を受け取れるようになると、薬剤師も24時間対応する必要があるでしょう。当然、シフト制や交代制になりますが、深夜帯に働いてしっかり稼げるようになります。ビデオ通話やチャットツールの活用といったデジタルスキルの習得も求められます。
調剤薬局で働く薬剤師にはOTC医薬品の知識が不足しがちです。OTC医薬品の数は多く、新商品も続々と発売されるため、常に勉強する姿勢が求められるでしょう。
3.濫用のおそれのある医薬品の販売制限
OTC医薬品のオンライン服薬指導が開始されますが、全ての医薬品が対象ではありません。若者によるオーバードーズ(過剰服薬や過剰摂取)の問題を受け、咳止めや鎮痛薬など「濫用のおそれのある医薬品」の販売には新たな制限が設けられます。
若年層へ販売する際、大容量製品または複数個の販売が禁止されます。若年層に小容量製品を販売する場合、若年層以外でも大容量製品もしくは複数個を販売する場合は、対面かオンラインでの指導が義務づけられます。薬剤師は購入者に他の薬局等での購入の状況、氏名、年齢、多量購入の理由などの確認・報告が必要です。
ドラッグストアで働く薬剤師に大きな影響があるものと思われます。該当する医薬品を販売する場合、お客様に詳しく話を聞く必要がありますが、断られたり、嫌な顔をされたりすることも多いでしょう。ただしお客様の健康を守るため、親しみを込めつつも厳格に対応する姿勢が求められます。
4.薬局の機能等のあり方の見直し
国は薬局に地域医療の担い手としての活躍を期待しています。外来患者への調剤・服薬指導、在宅患者への対応だけでなく、医療機関や他の薬局等との連携、地域住民への相談対応など、地域住民のための幅広い活躍を求めています。
かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師の推進もそのひとつです。複数の病院を受診し、複数の薬局を利用していると、効果が重複する薬や同時に服用すると健康被害がでる薬などに気づきにくくなります。かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師がいれば、重複や飲み合わせの確認がしやすく健康被害を防げます。
今回の法改正では、薬局を選びやすくなるよう薬局には情報の報告義務が課され、公表制度が整備されます。また「健康増進支援薬局」という新たな認定制度が創設されます。
処方箋の受付、調剤といった流れだけでなく、地域住民と積極的に交流する姿勢が求められます。一人の患者様の体調管理を長きに渡ってサポートする業務が増える見通しです。
5.零売薬局が原則禁止に
これまで処方箋医薬品以外の医療用医薬品については、処方箋なしでの販売は禁止されていませんでした。今回の法改正により、例外を除き医療用医薬品の一部を処方箋なしで販売する「零売薬局」が禁止されます。
例外となるのは、医師の処方で服用している医療用医薬品が手元になく、一般用医薬品では代替できない、災害・感染症拡大などによって薬局で医療用医薬品を販売する必要があるなど、やむを得ない場合のみです。なお、漢方薬や生薬は一般用医薬品から医療用医薬品に転用されてきた経緯があるため、販売に支障がないよう配慮されます。
6.処方箋等の保存期間が5年に
薬局では、調剤済みの処方箋と調剤録の保存期間は3年間です。しかし、現在は医療機関との情報共有が進められていることから、医師や歯科医師の診療録の保存期間である5年間に合わせて、薬局での保存期間も5年間に変更されます。保管ルールが変わることで、仕事の流れが一部変更になるでしょう。
7.より活発な創薬が行われる環境の整備
「ドラッグ・ラグ」「ドラッグ・ロス」の問題を受け、条件付き承認制度の適用拡大、日本の創薬力強化が盛り込まれます。
希少で患者数が少ない疾患や重篤かつ代替の治療法がない疾患を対象に、探索的臨床試験等で、一定程度の有効性・安全性が確認され、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合は、承認後に検証的臨床試験等を行うことが認められます。これにより、未承認薬だから薬が使えないとあきらめていた患者様の選択肢が増える見込みです。
創薬スタートアップ支援も盛り込まれ、革新的な新薬の実用化を支援するための基金が設置されました。今まで以上に新薬が登場するスピードが速まるでしょう。薬剤師は働きながらも、常に新薬の勉強が必要です。
8.医療用医薬品等の安定供給体制の強化等
ジェネリック医薬品を中心に供給不足の状況が続いています。海外での製造トラブルや製造販売業者などの不適切な製造もあり、医療用医薬品の約20%が限定出荷・供給停止というのが現状です。
今回の法改正では、医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の協力要請などが定められました。また、電子処方箋管理サービスのデータを活用して需給状況のモニタリングを行い、異変があった場合はすぐに対応できるような体制が整えられます。
製薬企業に勤める薬剤師は仕事内容が大きく変わる可能性があります。安定供給が行われれば、調剤薬局で患者様にお渡しする薬が入荷できないというトラブルが減少する見込みです。
9.医薬品等の品質及び安全性の確保の強化
医薬品は時に体に害を及ぼすことがあります。今回、製造販売業者における品質保証や安全管理のガバナンスを強化する組織体制が見直され、医薬品製造販売業者に「品質保証責任者」および「安全管理責任者」の設置が義務づけられました。医療費抑制、ジェネリック医薬品の安定供給に向けて、後発医薬品企業の再編や設備投資を支援する「後発医薬品製造基盤整備基金」も創設されます。
これから求められる薬剤師像
ここまで見てきてわかるように、これからの薬剤師には高いコミュニケーション力が求められます。今回の法改正は、2015年に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビジョン」において示された、薬剤師の「対物業務から対人業務へ」の流れが強化された形といえます。
これからの時代に活躍できる薬剤師になるために、高いコミュニケーション力、患者様に合わせた服薬指導のほか、オンラインチャットやICT機器の操作スキルを高めておきましょう。コミュニケーションは患者様対応だけでなく、医師や看護師、介護福祉士、ケアマネジャーなど他職種との連携が必要な在宅医療の場でも求められます。
かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師も推進されるため、患者様の服薬履歴の継続的な管理、残薬管理と調整のスキルも高めておくと良いでしょう。同時にOTC医薬品の専門知識強化、最新の医療・薬学知識のアップデートも欠かせません。
薬剤師として成長していきたいと思ったら、「アプロ・ドットコム」に相談を
今働いている職場で薬機法改正に合わせて取り組みが行われ、活躍の場があるなら、そのままステップアップをめざしたほうがよさそうです。ただし、「今の職場は自分が望んでいるキャリアと異なる」「得意な領域を活かせない」と判断した場合は、早めの転職がおすすめです。
「アプロ・ドットコム」は薬剤師の転職支援に特化した転職支援サービスです。これまで多くの薬剤師のキャリアアップやステップアップを支援してきました。あなたの希望に合わせて、経験豊富なキャリアアドバイザーが法改正後の変化もふまえて、それぞれの経験やスキルを活かせるキャリアと求人を提案します。まずは、お気軽にご相談ください。
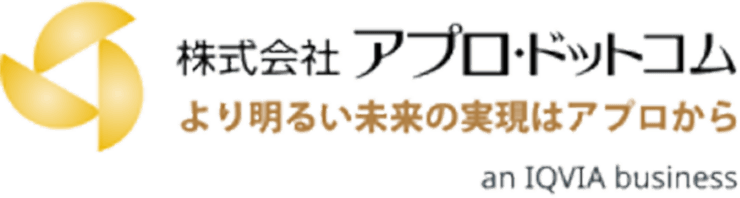
 はじめての方
はじめての方






 気になる求人
気になる求人