スタッフブログ
薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の薬剤師求人、派遣や単発派遣に関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。
薬剤師の仕事・キャリア
2025.04.08
専門薬剤師と認定薬剤師は何が違う?取得条件や専門分野、活かせるステージをチェック

- 薬剤師
- 求人
- 仕事
- アプロ・ドットコム
- 認定薬剤師
- 専門薬剤師
薬剤師として働くなかで、いずれは専門薬剤師や認定薬剤師として活躍したいと思っている人もいるでしょう。実は薬剤師には特定分野のスキルの証明になるものや、今後の需要が見込まれるものなど、多種多様な認定資格があります。取得することでよりやりがいが持てる、活躍の場が広がるなど、仕事の仕方や環境も変わってくるでしょう。
今回は、薬剤師の認定資格である専門薬剤師と認定薬剤師について、種類や取得の条件、活躍の場などを詳しく紹介します。それぞれの違う点も理解して、ぜひ将来に向けて参考にしてください。
まずは、薬剤師の認定制度について知っておきましょう。
薬剤師認定制度とは
医学・薬学の高度化や細分化にともなって、特定の医療分野などで高度な知識や経験を持つ薬剤師を認定する制度のことです。集合研修や自己研修により、一定の期間に定められた単位を取得することで、有効期限付きの証明を受けられます。認定制度には「生涯研修認定制度」「特定領域認定制度」「専門薬剤師認定制度」の3つがあり、これらの制度で認定された薬剤師が「認定薬剤師」です。
「専門薬剤師」と「認定薬剤師」との違い
どちらも専門的な知識と技術を有する認定薬剤師ですが、専門薬剤師の資格取得は試験に合格する必要があります。認定薬剤師のなかで各領域の実務経験を重ね、学会や論文発表、症例報告、専門領域での薬物療法に関する研修などを経たのち、取得できるのが領域別の「専門薬剤師」です。認定薬剤師にしか存在しない資格、逆に専門薬剤師にしかない資格などもありますが、一般的には専門薬剤師のほうが難易度は高い傾向がありす。
ここからは、「認定薬剤師」「専門薬剤師」それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
専門薬剤師
病棟や地域包括システムの医療チームのなかで、医師や看護師などの多職種と連携して働く薬物療法のスペシャリスト。医療チームの負担軽減につながるほか、認定薬剤師の指導・監督的な立場も求められます。認定薬剤師の上位資格である専門薬剤師をめざす場合は、同分野の認定薬剤師の資格を取得している必要があることが多いでしょう。
・専門薬剤師の種類
専門薬剤師の認定機関はいくつかあり、認定機関によって資格が異なります。
| 資格名 | 認定機関 |
| 感染制御専門薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| 精神科専門薬剤師 | |
| 妊婦・授乳婦専門薬剤師 | |
| HIV感染症専門薬剤師 | |
| 医療薬学専門薬剤師 | 日本医療薬学会 |
| 地域薬学ケア専門薬剤師(がん) | |
| がん専門薬剤師/薬物療法専門薬剤師 | |
| 禁煙専門薬剤師(日本禁煙学会) | その他の学会、職能団体 |
| 医薬品情報専門薬剤師(日本医薬品情報学会) | |
| 腎臓病薬物療法学会専門薬剤師(日本腎臓病薬物療法学会) | |
| 栄養サポート(NST)専門薬剤師(日本静脈経腸栄養学会) |
・必要な資格・条件
専門薬剤師になるための要件も認定機関や資格によって異なります。基本的には、基礎となる研修認定薬剤師の資格を取得し、各領域の認定薬剤師を取得します。実務経験を重ね、学会や論文発表、症例報告、専門領域での薬物療法に関する研修などを経たのち、専門薬剤師をめざすのが一般的です。
押さえておきたい専門薬剤師
専門薬剤師で押さえておきたい資格を5つ紹介しましょう。専門薬剤師の取得要件は複雑なものが多いため、詳細はそれぞれの認定機関でしっかり確認してください。
・がん専門薬剤師
高度ながん治療に関する知識と技術を持ち、より安全で的確ながん薬物療法を支援できることを証明する資格。がん治療におけるチーム医療の一員として活躍できるとともに、抗がん剤の新薬に関する行政の審査機関や治験などでも活躍できます。
・感染制御専門薬剤師
感染の制御を目的に、適切な薬物療法の提案や情報提供をする薬のスペシャリストであることを証明する資格。感染症や合併症のリスクが高い患者様に対して、適切な薬物投与と副作用の管理などのほか、院内感染予防に関する情報提供、薬物管理および、医療従事者に対する教育・啓発など幅広い活躍が期待されます。「感染制御認定薬剤師」の上位資格です。
・精神科専門薬剤師
精神疾患に対する薬物療法を有効かつ安全に行うことのできる認定資格。メンタルヘルスケアに対する需要は年々高まっており、活躍の場が広い領域。「精神科薬物療法認定薬剤師」の上位資格です。
・妊婦・授乳婦専門薬剤師
胎児や乳児の状態に配慮しながら、母子双方に安全かつ適切な薬物療法を提供する知識と技術を証明する資格。「授乳婦薬物療法認定薬剤師」の上位資格です。
・HIV感染症専門薬剤師
HIV治療で重要となる薬物療法について、高度な知識や技能を持っていることを証明する資格。病院や薬局だけでなく、最近低年齢化や増加が懸念されるSTD(性感染症)の一種として、HIV感染症予防を啓蒙する講師などでも活躍が期待されます。「HIV感染症薬物療法認定薬剤師」の上位資格です。
認定薬剤師
薬剤師としての知識や技術があると認められることで、的確な助言やサポートができます。認定薬剤師は、最近需要が高い「かかりつけ薬剤師」の要件であったり、管理薬剤師は認定薬剤師であることが推奨されていたりと今後も高い需要が見込まれます。さらに調剤報酬改定では地域支援体制加算の算定にかかりつけ薬剤師としての服薬指導実績が必要になるなど、認定薬剤師の資格を取得することが薬剤師として働くうえでも重要になっています。
・認定薬剤師の種類
認定機関はさまざまあり、種類も数多くあります。自分に合った資格、専門薬剤師も含め将来的にめざしたい資格に絞るのがおすすめです。
| 分野名 | 資格名 | 認定機関 |
| 悪性腫瘍 | がん薬物療法認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| 外来がん治療認定薬剤師 | 日本臨床腫瘍薬学会 | |
| 緩和薬物療法認定薬剤師 | 日本緩和医療薬学会 | |
| 核医学 | 核医学認定薬剤師 | 日本核医学会 |
| 感染症 | 感染制御認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| HIV感染症薬物療法認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 | |
| 抗菌化学療法認定薬剤師 | 日本化学療法学会 | |
| 外来抗感染症認定薬剤師 | 日本化学療法学会 | |
| 腎疾患 | 腎臓病薬物療法認定薬剤師 | 腎臓病薬物療法認定薬剤師 |
| 内分泌 | 糖尿病薬物療法認定薬剤師 | 日本くすりと糖尿病学会 |
| 高齢者 | 老年薬学認定薬剤師 | 日本老年薬学会 |
| 認知症 | 認知症研修認定薬剤師 | 日本薬局学会 |
| 皮膚科 | 日本褥瘡学会認定師 | 日本褥瘡学会 |
| 精神科 | 精神科薬物療法認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| 産科・婦人科 | 妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| 小児科 | 小児薬物療法認定薬剤師 | 日本薬剤師研修センター |
| 救急・中毒医療 | 救急認定薬剤師 | 日本臨床救急医学会 |
| プライマリ・ケア在宅医療 | プライマリ・ケア認定薬剤師 | 日本プライマリ・ケア連合学会 |
| 臨床薬理 | 在宅療養支援認定薬剤師 | 日本在宅薬学会 |
| 臨床試験 | 日本臨床薬理学会認定薬剤師 | 日本臨床薬理学会 |
| 実務実習 | 日病薬認定指導薬剤師 | 日本病院薬剤師会 |
| 多領域 | 研修認定薬剤師 | 日本薬剤師研修センター |
| 医療薬学専門薬剤師 | 日本医療薬学会 | |
| 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 日本病院薬剤師会 | |
| その他 | 漢方薬・生薬認定薬剤師 | 日本薬剤師研修センター |
| 公認スポーツファーマシスト | 日本アンチ・ドーピング機構 |
(2023年6月時点)
・必要な資格・条件
一般的には、申請をして研修を受講し、単位を取ります。受講後に認定申請を行い、認定されるという流れです。認定薬剤師の認定要件は、各認定資格によって異なります。詳細は各認定団体の取得要件を確認しましょう。
気をつけたいのは、薬剤師免許とは違い、認定薬剤師には有効期限があるということ。一定期間ごとに更新する必要があり、通常認定期間は3年から5年です。種類によって変わりますが、少なくとも期間満了までに一定の取得要件を満たし更新申請をする必要があります。
押さえておきたい認定薬剤師
認定薬剤師の種類は多く、何をめざすべきか迷う人もいるかもしれません。ここでは特におすすめの資格を6つ紹介します。
調剤薬局・調剤併設ドラッグストアで活躍できる資格
・認定薬剤師の基本「研修認定薬剤師」
認定薬剤師のなかで、もっともスタンダードで受験者が多く、薬剤師の資質の維持・向上に努め、薬学・医療知識があることを認定する資格です。e-ラーニングや集合研修、論文発表などを通じて、基礎薬学・医療薬学、衛生薬学、薬事関連法規といった幅広い分野を学びます。調剤薬局で需要が高まっている「かかりつけ薬剤師」になるための要件でもあり、最近では取得の有無が採用の基準になる場合もあるようです。
【取得要件】
研修を受講後、「認定申請日から4年以内に40単位以上」を取得
・セルフメディケーションのニーズ増加で注目の「漢方・生薬認定薬剤師」
漢方薬・生薬分野の専門知識を習得した、高い能力と適性を有する薬剤師として認められる資格。薬局やドラッグストアで、漢方薬の副作用や多剤併用の危険性のほか、OTC医薬品の利用法など、専門的な提案や服薬指導を行えます。
【取得要件】
・「漢方薬・生薬研修会」を修了(出席率要80%以上)
・薬用植物園実習を受講しレポートの提出(受験資格は研修会・実習受講後2年有効)
・上記研修会・実習修了後、試問試験に合格
・地域の健康窓口として期待される「プライマリ・ケア認定薬剤師」
医療に関する総合的なアドバイスを行える薬剤師として、健康福祉にかかわるさまざまな問題解決に取り組むスキルが評価される資格。服薬指導・支援はもちろん、医療全般における「生活習慣指導」「セルフメディケーション」「コミュニケーション能力」などに関する幅広いスキルが必要です。地域の健康窓口としても機能する薬局などで、かかりつけ医師・看護師などと連携して身近な相談相手として患者様をサポートします。
【取得要件】
・4年以内に指定の研修会・講座で50単位を取得
(学会関連の講座30単位以上・細則にある必須領域20単位・見学実習8単位)
・必要な単位を取った後、試験・審査を経て資格を取得
病院・診療所などの医療機関で活躍できる資格
・新型コロナウイルス流行で重要性が増した「感染制御認定薬剤師」
感染症治療や予防領域で適切・安全な薬物療法が行える薬剤師であることを認定する資格です。特に、新型コロナウイルスにより感染症対策についての重要性が再認識され、注目を集めています。医療現場での感染発生予防、感染対策などの正しい情報の発信・レクチャーなどのほか、患者様に合わせた薬物治療や感染対策を提案します。
【取得要件】
・3年以上の実務経験
・日病薬病院薬学認定薬剤師の取得(ただし、日本医療薬学会の専門薬剤師制度により認定された専門薬剤師であればこれを満たす)
・各種講習会をはじめとする所定の単位(20時間、10単位)以上履修 など
・日本人にもっとも多いがん治療に関わる「がん薬物療法認定薬剤師」
副作用、服薬管理、疼痛コントロールをはじめ、がん治療の薬物療法に関わる十分な知識と技術を持ち、質の高い薬物治療を実践する薬剤師として認定する資格。薬剤の専門家としてがん薬物治療のチームに参加し、医師や患者に説明や指導なども行います。
日本人の死因のトップであり、増加しているがん患者の治療において最適な薬物治療に対応できる薬剤師が必要とされ、他の資格と比べても特にニーズの高い資格です。今後は病院のみならず、在宅医療でも需要が増すでしょう。
【取得要件】
・薬剤師として3年以上の実務経験
・申請時に病院または診療所で、がん薬物療法に3年以上かつ、申請時に引き続いて1年以上従事していること
・がん患者への薬剤管理指導実績が50症例(複数の癌種)以上
・各種講習会をはじめとする所定の単位(40時間、20単位)以上履修(ただし、日本病院薬剤師会主催のがん専門薬剤師に関する講習会を12時間、6単位以上要取得)
など
・がん治療の緩和ケアチームで活躍できる「緩和薬物療法認定薬剤師」
がん治療の緩和ケアチームにおいて、薬剤師が他職種と連携して安全な薬物療法を推進するための資格。緩和薬物療法に用いる薬剤は、用量や副作用の面などで取り扱いが難しいものが多く、薬物療法の選択肢も増えてきているため、専門知識を持つ薬剤師の活躍が期待されています。
【取得要件】
・薬剤師として5年以上の実務経験
・緩和医療領域における薬剤管理指導(服薬指導)の実績「病院等に勤務する薬剤師は30症例」、「保険薬局に勤務する薬剤師は15症例」を提示(過去6年以内のもの)
など
その他にも「DLM認定薬剤師」は薬剤師全般の基礎知識の証明になり、スキルアップにも役立ちます。また、高齢化社会が進むなかで在宅療養の必要性が高まっており、「在宅療養支援認定薬剤師」も在宅医療を実施する地域密着型の薬局で働く薬剤師におすすめの資格でもあります。
「小児薬物療法認定薬剤師」や「妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師」は、小児科や産婦人科の門前薬局で重宝されます。救急医療や病院でのキャリアアップをめざす人にとって「救急認定薬剤師」は取得しておきたい資格といえるでしょう。
これらの認定薬剤師よりも、より専門的な知識や技術があることを認定するのが専門薬剤師です。上位資格がある場合は、積極的にチャレンジしてください。
「アプロ・ドットコム」で経験を積んで専門薬剤師・認定薬剤師をめざそう!
専門薬剤師・認定薬剤師になることで医師や看護師、患者などからの信頼が厚くなるほか、他の薬剤師との差別化につながり転職時に有利になります。専門薬剤師はもちろん、職場によっては認定薬剤師資格を持っていることが評価されるケースもあるので、キャリアアップにつながります。
資格手当や昇給など、年収アップも期待できるでしょう。薬剤師の就職・転職に特化した人材サービス「アプロ・ドットコム」なら、さまざまな求人が見つかります。経験を積んで、将来的に専門薬剤師や認定薬剤師として活躍できる薬剤師をめざしましょう。
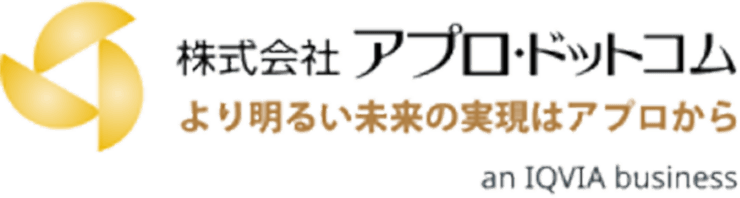
 はじめての方
はじめての方






 気になる求人
気になる求人