スタッフブログ
薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の正社員・アルバイト求人、派遣や単発派遣、パートに関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。
記事一覧
-

セミナーのお知らせ
2025.05.08NEW
【5/21まで見逃し配信中】『薬剤師のための賢い資産形成 ~4つの視点で築く豊かな未来~』オンラインセミナー
先日、2025年4月21日(月)に開催された好評のオンラインセミナー『薬剤師のための賢い資産形成~4つの視点で築く豊かな未来~』の見逃し配信が決……
Read More -

薬剤師の仕事・キャリア
2025.04.30
「今すぐ転職しないほうがいい薬剤師」の5つの共通項
薬剤師として働いている人のなかには、ずっと今の職場で働き続けるのか、転職したほうが良いのか迷っている人もいるでしょう。薬剤師は国家資格なので転職し……
Read More -

セミナーのお知らせ
2025.04.28
【5/16開催】無料オンラインセミナー『薬剤師のための“心と体が潤う食薬ドリンク”』
最新オンラインセミナーのご案内です。食薬の第一人者であり、漢方薬剤師、国際中医師である大久保愛先生を講師にお招きし、「水と私たちの深い関係』」……
Read More -

アプロママ特集
2025.04.28
ママ薬剤師が働きやすい職場を選ぶための4つのポイント
「ママになっても仕事をがんばりたい」「育児と仕事の両立をしたい」「薬剤師のキャリアを失いたくない」など、これからの働き方に悩んでいるママ薬剤師は少……
Read More -

薬剤師の仕事・キャリア
2025.04.25
薬剤師の転職で円満退社するための退職理由と伝え方、ダンドリをチェック
転職を決心したら、なるべくスムーズに退職して次のキャリアを始めたいものです。薬局業界は広いようで狭く、意外な人同士が実は知り合いだったという話をよ……
Read More -

派遣の基礎知識
2025.04.22
薬剤師の単発派遣・単発バイトの始め方ガイド2025
薬剤師の仕事探しというと、フルタイムや毎週何曜日など定期的に長期間働くことを見越した業務をイメージする人が多いのかもしれません。薬剤師にも、単発派……
Read More -

薬剤師の仕事・キャリア
2025.04.18
派遣薬剤師が長く働けるようになるために必要なこと
派遣薬剤師の働き方に興味がある人のなかには、できるだけ長く派遣薬剤師として活躍していきたいと思っている人もいるでしょう。しかし、「派遣ではそこまで……
Read More -

派遣の基礎知識
2025.04.15
薬剤師の「派遣」「単発派遣」の違いとメリット・デメリット
薬剤師派遣と聞くと、数ヵ月から数年単位で働く派遣を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、派遣には期間が定められた契約で働く一般派遣と、1日から1ヵ……
Read More -

セミナーのお知らせ
2025.04.14
終了しました)【4/24開催】無料オンラインセミナー『薬剤師【派遣】キャリアアドバイザーの活用法とよくある質問』
派遣薬剤師としての働き方や最新情報を知りたい方へ!派遣の基礎知識から求人の種類・特徴、メリット・デメリット、登録方法やサポート体制まで、皆様の疑……
Read More -

派遣の基礎知識
2025.04.11
派遣薬剤師で失敗しないために人材派遣会社に聞いておきたいこと
派遣薬剤師として働き始めたものの、「こんなはずじゃなかった」と感じたことがある人もいるでしょう。原因は派遣のルールを知らなかった、自分のスキルが求……
Read More
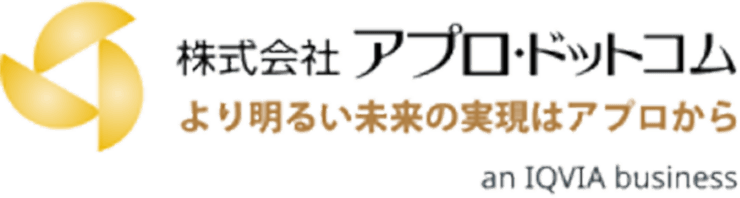
 はじめての方
はじめての方

 気になる求人
気になる求人